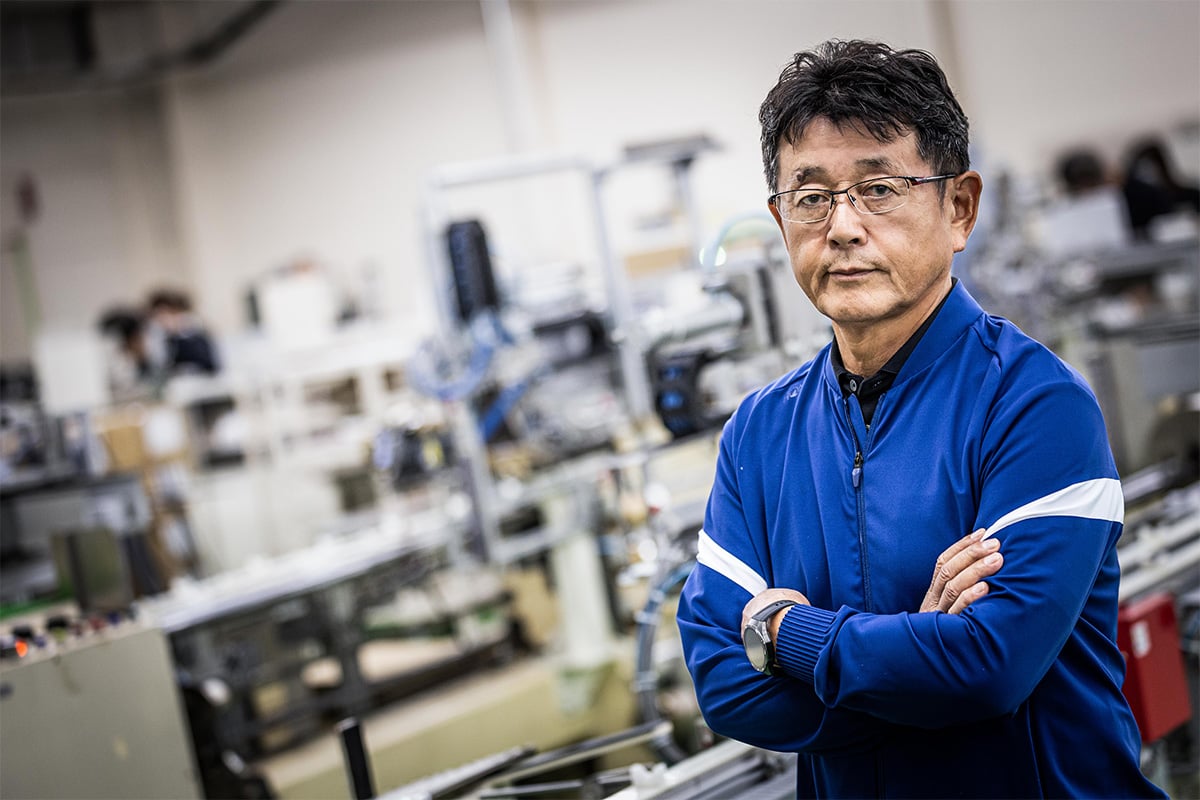- ゴルフのニュース|総合ゴルフ情報サイト
- 記事一覧
- コラム
- 転がしアプローチが安全とは限らない!今平周吾が障害物もないのに球を上げた理由
多くのツアープロのコーチとして活躍している石井忍氏が、“ここはスゴイ”と思った選手やプレーを独自の視点で分析します。今回注目したのは、国内男子ツアー「アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ2022」で優勝した今平周吾のアプローチです。
245ヤードの16番パー3でUTを選択した理由
「アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ2022」が開催されました。優勝したのは今大会で唯一、4日間ともアンダーパーでプレーした今平周吾選手。通算8アンダーで今季初勝利、通算6勝目を挙げました。

戦いの舞台になった大洗ゴルフ倶楽部は、日本有数の難コースとして知られています。
今平選手自身が「今週は曲げたらダメ」「ボギーを打たなければチャンスはある」と語っていたように、無理をせずコースと自分との戦いに徹していた印象を受けました。
象徴的だったのは、最終日16番(パー3)のマネジメントです。この16番と17番(パー4)は、“難関・大洗”の中でも特に難度が高いホール。
15番(パー5)でバーディーを奪いトップに立った今平選手は、この2ホールをパーでしのげば勝利をグッと引き寄せることができる状況でした。
16番は、245ヤードと距離のあるパー3。今平選手はティーショットでユーティリティーを手にします。
ピンまで届かせるなら1つ上の番手がベター。しかし、それではショットの精度が下がり、思わぬミスを招く可能性があります。
リスクを伴う1オン狙いを避け、精度の高いユーティリティーで「エッジでもOK」というマネジメントをしたわけです。
結果、今平選手はこのショットをグリーン手前まで運びます。次打は、ボールからエッジまで5ヤード程度、エッジからピンまで15ヤード程度。
ボールからカップの間に障害はなく、足を使ったアプローチの方が安全そうに思えるシチュエーションでした。
しかし、今平選手はここでフワっと球を上げる打ち方を選択します。
彼はなぜ、転がすアプローチを選ばなかったのか。その理由は、エッジからカップまでがスネークラインだったからです。
曲がりを想像しづらいラインの上を転がすよりも、球を上げてスネークラインを飛び越え、カップ付近に着弾させたほうがリスクは少ないと判断したのです。
今平選手はこのアプローチに成功し、狙い通りにパーをセーブ。難しい17番と最終18番もパーとして、優勝を手にしました。
上げるアプローチは、エッジからカップまでの距離が近い時やバンカー越え、打ち上げなどの限られた状況の特殊な打ち方だと思う人もいるかもしれません。
しかし、今回の今平選手のように、一見転がしがベターと思われるシチュエーションでも、上げたほうが寄る可能性が上がることがあります。
ライが良ければ“転がし一択”ではなく、球を上げたらどうなるかを考えてアプローチを選択すると、プレーの幅が生まれるはずです。
アプローチで球をフワッと上げる方法

ちなみに“上げる”というと、腰を落としてフェースを思い切り開き、カット軌道で大胆に振るショットを想像するかもしれませんが、もっと簡単に球を上げる方法があります。
フェースを少し開き、ハンドファーストで構えずに、グリップエンドをおへそに向けてアドレスしてください。
そして、手首をリリースして振ればOK。これだけで球の高さをアレンジできます。上げるアプローチが苦手な人は、ぜひ試してみてください。
今平 周吾(いまひら・しゅうご)
1992年生まれ、埼玉県出身。高校1年時の「日本ジュニア」(08年)で優勝し、翌年から高校を中退して渡米。IMGゴルフアカデミーで腕を磨く。帰国後、11年にプロ転向。14年は国内下部ツアーで賞金王に。15年にレギュラーツアー初シードを獲得し、17年に初勝利。18年、19年は2年連続賞金王に輝いた。通算6勝。ダイヤ所属。
石井 忍(いしい・しのぶ)
1974年生まれ、千葉県出身。日本大学ゴルフ部を経て1998年プロ転向。その後、コーチとして手腕を発揮し、多くの男女ツアープロを指導。「エースゴルフクラブ」を主宰し、アマチュアにもレッスンを行う。
最新の記事
pick up
ranking